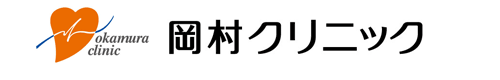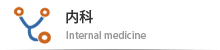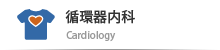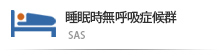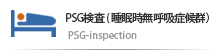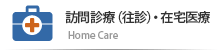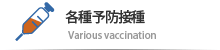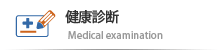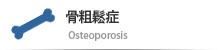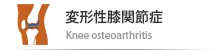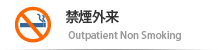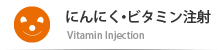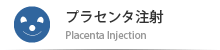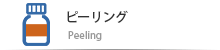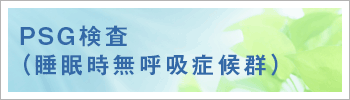睡眠時無呼吸症候群=SAS(Sleep Apnea Syndrome)は睡眠中に幾度も呼吸が停止する症状です。医学的な定義としては、10秒以上気道の空気の流れが止まった状態を「無呼吸」としており、この無呼吸が一晩(7時間の睡眠中)に30回以上、あるいは1時間につき5回以上ある場合、睡眠時無呼吸とされます。
睡眠中の症状であるためなかなか自覚できず、知らず知らずのうちに日常生活に多くのリスクが生じる可能性がある点が特徴です。
当院では睡眠時無呼吸症候群の検査を行っています。
お電話もしくは当院受付でお問い合わせください。
![]()
■症状
下記のような症状がある場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。
少しでも気にかかる事などありましたら、ご相談ください。
・いびき
・睡眠時に呼吸が止まる
・睡眠時に呼吸が乱れたり、息苦しさを感じる
・幾度度も目覚める
・寝汗
・熟睡感を得られない
・すっきり起きられない
・身体が重い
・集中力が続かない
・慢性的な疲労感
![]()
![]()
■呼吸が止まる原因
●閉塞性睡眠時無呼吸タイプ(OSA)
上気道に十分なスペースがなくなり、空気が通りにくくなることによって呼吸が止まってしまうタイプです。SASの患者様のおよそ9割がこのタイプに該当します。
主な要因として挙げられるのは、首や喉まわりの脂肪沈着や扁桃肥大や、舌の付け根や軟口蓋(口腔上壁後方の軟らかい部分)などによる喉および上気道の狭窄です。
また、元々の骨格が小さいと上気道のスペースは圧迫されます。元からスペースが狭い場合にはさらに詰まりやすくなります。
●中枢性睡眠時無呼吸タイプ(CSA)
閉塞型とは違い、呼吸中枢の異常によって脳から呼吸指令が出なくなり、気道の閉塞なしに呼吸停止する症状です。肺や胸郭、呼吸筋、末梢神経にはこれといった異常がなくても無呼吸が生じるため、いびきや日中の眠気など、自覚しにくいのが特徴です。
OSAの場合、気道が狭くなるために呼吸しようと努力しますが、CSAの場合は気道は開いたままであるにも関わらず、自覚症状がないため努めて呼吸しようとしません。
病気のメカニズムは不明な場合も多いですが、慢性心不全の30~40%の方に見られるとされています。この異常呼吸のある場合、心臓の機能が同じようでも余命に差が出るという事もわかってきています。
●中枢性睡眠時無呼吸タイプ(CSA)
閉塞型とは違い、呼吸中枢の異常によって脳から呼吸指令が出なくなり、気道の閉塞なしに呼吸停止する症状です。肺や胸郭、呼吸筋、末梢神経にはこれといった異常がなくても無呼吸が生じるため、いびきや日中の眠気など、自覚しにくいのが特徴です。
OSAの場合、気道が狭くなるために呼吸しようと努力しますが、CSAの場合は気道は開いたままであるにも関わらず、自覚症状がないため努めて呼吸しようとしません。
病気のメカニズムは不明な場合も多いですが、慢性心不全の30~40%の方に見られるとされています。この異常呼吸のある場合、心臓の機能が同じようでも余命に差が出るという事もわかってきています。
![]()
![]()
■治療について
◆CPAP
CPAP装置からエアチューブを通して鼻に装着したマスク、気道へと空気が送り込みます。気道に空気を送り続けることで気道を開存させておき、睡眠中の無呼吸を防ぐのです。
風圧でのどの中のスペースが確保されることで、組織が強制的に押し開かれ、鼻でスムースに呼吸することが可能になります。
継続することでいびきがなくなり、眠気も改善され、ひいては合併症の予防につながります。
◆マウスピース
下あごを上あごより前方に固定させて上気道を広く保ちます。気道の広さが保たれることで、いびきや無呼吸の発生を防ぎます。
ただし、症状が重めの場合は治療効果が不十分とされる報告もあるため、あらかじめ医師と相談して使用を決めるのが良いです。
※マウスピース作成は、専門の歯科医にお願いするのが良いです
![]()
![]()
■日常生活に取り入れられる対策
睡眠時無呼吸症候群は日常生活の中で実践できる対策もあります。
・横向きに寝ること
舌が上気道を塞ぐのを防ぐ、最も簡単な対策は身体を横向きにして寝ることです。
真横でなくとも、すこし傾けるだけでも上気道に空気が通りやすくなります。
・鼻呼吸の習慣
口呼吸は大量の空気が入ってくるため、狭くなった上気道を通る際に喉を振動させ、いびきが発生します。鼻呼吸するだけでも症状に変化が見られることもあります。
・飲酒を控える
アルコールによって筋肉がゆるむと、舌によって上気道がふさがれやすくなります。
こうした生活習慣の改善による対策もできますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
・ダイエット
舌や喉の周囲に余剰脂肪があると上気道が狭くなりやすいため、ダイエットもひとつの対策になります。
![]()
岡村クリニック
〒343-0111 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏820-1
[TEL] 048-991-7203
駐車場完備
▼診療時間
月・火・水・金 9:00~12:00 15:00~19:00
(15:00~17:00往診優先)
土 9:00~12:00 ▲15:00~18:00
(15:00~17:00往診優先)
※院外処方は18:30まで。
ご希望の方は18時までの受診をお願いします。
休診日 木・日・祝日
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー |
| 15:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ▲ | ー | ー |